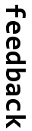自分の職場に突然親父が来た。
何の目的で来たのか判らず動揺したが、元々来る予定だったような気もした。親父が関係している団体に関する要綱の締結の件だったかもしれない。何も今来なくても良いじゃないかと思ったが、別に今来ても構わない気持ちになった。
彼が上司連中と会うのは初めてだが、如才なく社交的な親しさをもって話している。いつものことながら、話している内容はぼんやりして聞き取れない。顔を緩めて「久しぶりですねぇ」を連発した。周りの連中には、初めて来る場所なのに何が久しぶりなのか判らないだろうが、定年退職して何年も経つので「オフィス」という雰囲気が嬉しいのだろうということが自分には判った。元来仕事人間なのだ。
「うちの子はどうですか」みたいな話をしている。碌な話は出ないだろうが、上司もそれをあからさまに言うことはしないだろう。「うちの子は耳が聞こえないのですが、それでも応用は出来ると思うんですね」と言う親父の言葉だけは聞こえた。
自分は、もうまもなく事務仕事を切り上げて帰るつもりだったので、一緒に車に乗せてってくれないかと頼んだ。机の上は散らかっているが、そこそこに体裁を整えて帰ることにした。親父に渡す文書の入ったA4の封筒があったので、彼に渡した。
外に出ると辺りは日が落ちて暗く、街灯が青く光って空気を透明にしていた。
車に乗って親父と帰宅した。自分が運転しているのか親父が運転しているのか判らなかったが、親父は自分が渡した封筒から書類を大事そうに引っ張り出した。見ると、書類には契約書のような割印が、2つか3つ押してあった。その内一つはやたらとくっきりして、もう一つは反対にひどくぼやけていた。
親父は「これは大したものだよ」と感慨深げに呟いた。
自分は毎日そうした書類を作成していて、そんなのは全て何かの丸写しで、内容も適当で、上司達も中身を見ることもなく私用の合間についでに事務をこなして決裁していることを知っているので、「そういうものかね」と返事をした。言った後で、余計なことを言ってしまったかなと反省した。問題は中身ではなくて、行政が交付したという点に価値があるのだ。その書類をもらうために、民間の人達は無駄な書類を苦労して揃えて、やっとの思いで申請するのだ。毎日引き出しを開け閉めしてるだけのような作業をこなしていると、そうした感覚が麻痺してくる。親とはいえども、内情を漏らすようなことをして、世間を惑わせてはならない。
親父が何か言ってきたら、今度は意に沿う返事をしようと身構えたが、何も言って来なかった。
二人で黙って車に乗っていた。座る位置から考えると自分が運転席にいることになるが、ハンドルは持っていなかった。
車は、雨で光る街灯の中を黙々と進んでいった。もう直ぐ、家に着くなと頭の隅で考えた。
何の目的で来たのか判らず動揺したが、元々来る予定だったような気もした。親父が関係している団体に関する要綱の締結の件だったかもしれない。何も今来なくても良いじゃないかと思ったが、別に今来ても構わない気持ちになった。
彼が上司連中と会うのは初めてだが、如才なく社交的な親しさをもって話している。いつものことながら、話している内容はぼんやりして聞き取れない。顔を緩めて「久しぶりですねぇ」を連発した。周りの連中には、初めて来る場所なのに何が久しぶりなのか判らないだろうが、定年退職して何年も経つので「オフィス」という雰囲気が嬉しいのだろうということが自分には判った。元来仕事人間なのだ。
「うちの子はどうですか」みたいな話をしている。碌な話は出ないだろうが、上司もそれをあからさまに言うことはしないだろう。「うちの子は耳が聞こえないのですが、それでも応用は出来ると思うんですね」と言う親父の言葉だけは聞こえた。
自分は、もうまもなく事務仕事を切り上げて帰るつもりだったので、一緒に車に乗せてってくれないかと頼んだ。机の上は散らかっているが、そこそこに体裁を整えて帰ることにした。親父に渡す文書の入ったA4の封筒があったので、彼に渡した。
外に出ると辺りは日が落ちて暗く、街灯が青く光って空気を透明にしていた。
車に乗って親父と帰宅した。自分が運転しているのか親父が運転しているのか判らなかったが、親父は自分が渡した封筒から書類を大事そうに引っ張り出した。見ると、書類には契約書のような割印が、2つか3つ押してあった。その内一つはやたらとくっきりして、もう一つは反対にひどくぼやけていた。
親父は「これは大したものだよ」と感慨深げに呟いた。
自分は毎日そうした書類を作成していて、そんなのは全て何かの丸写しで、内容も適当で、上司達も中身を見ることもなく私用の合間についでに事務をこなして決裁していることを知っているので、「そういうものかね」と返事をした。言った後で、余計なことを言ってしまったかなと反省した。問題は中身ではなくて、行政が交付したという点に価値があるのだ。その書類をもらうために、民間の人達は無駄な書類を苦労して揃えて、やっとの思いで申請するのだ。毎日引き出しを開け閉めしてるだけのような作業をこなしていると、そうした感覚が麻痺してくる。親とはいえども、内情を漏らすようなことをして、世間を惑わせてはならない。
親父が何か言ってきたら、今度は意に沿う返事をしようと身構えたが、何も言って来なかった。
二人で黙って車に乗っていた。座る位置から考えると自分が運転席にいることになるが、ハンドルは持っていなかった。
車は、雨で光る街灯の中を黙々と進んでいった。もう直ぐ、家に着くなと頭の隅で考えた。